バイク ツーリング に出かけると避けられないのが、観光地周辺や主要高速道路の「渋滞」でしょう。渋滞路では多くのライダーが、止まっているクルマの間を走り抜けていく、通称「 スリ抜け 」をしていますが……これは違法なのか、合法なのか? この点についてまとめた記事を見つけたので、シェアします。
現場の警察官にインタビューした この記事によれば……「右側から抜く」が守られていれば、原則として取り締りを受けにくいとのことでした。その要旨は以下の通りです。
- 法規上「すり抜け」という言葉は存在せず、その行為は「追い越し」とみなされる
- 追い越しや追い抜き(車線を越えずに前に出る)は右側からしか認められていない
- 赤信号で止まっているクルマの間を抜けていくときも右側からしか認められない
- 路側帯(歩道に接していない道路の 車道外側線の左側に設けられた 歩行者や自転車のためのスペース)を通ったら それだけで違反になる
- 片側2~3車線道路の間を抜けていくときは「左車線を走ってクルマの右側を追い抜く」なら大丈夫(右車線に出る場合は、右ウインカーを出して右車線から追い越し、左ウインカーを出して左車線に戻れば大丈夫) *いずれの場合も抜くクルマが停止していないと違反
さらに梶(K2 Bike TRAVEL代表)が「 スリ抜け 」時に心がけているのは、
■ウインカーを出さずに車線変更するクルマに出くわしても、避けられる(止まれる自信がある)速度で走ること
■君子危うきに近寄らないこと=車線変更したそうなクルマや挙動不審なクルマには近付かないこと
■ドライバーを刺激せず、忍者のように(何事もなかったように) スリ抜け ていくこと
です。
以前に…… スリ抜け 時のヘッドライトは「ハイビーム」と「ロービーム」のどちらがいいか?……をテストしてみたら、ロービーム のほうがベターという結論にたどり着きました。
「ハイビーム」にすると被視認性は高まるのですが、ドライバーのイライラ感を増幅するようで、幅寄せされる頻度が1.5倍から2倍に増えてしまったからです。ギラッと光ったミラーを見たら「見たほうにクルマが寄ってしまった」という理由もあるのでしょう。
むしろ「ロービーム」にして、前方左右のドライバーの動きを観察し、クルマが動かないと確信したときにだけ、ていねいに慎重に抜けていく。そんな走り方のほうが、自分もドライバーもストレスが少ないように感じています。
いずれにせよ、止む無く スリ抜け するときには
■「自分の身は自分で守る」
■「法律はどうあれ、こちらが事故を避けてあげる」
という気持ちが不可欠だと思います。
【補足】上記の表現(法律はどうあれ、こちらが事故を避けてあげる)がわかりにくいという声をいただいたので補足しておきます。
特に海運界では、法律的な優先権を超えて「機動力の高いほう(釣り船やモーターボート)が、機動力の低いほう(タンカーなど)を避ける=事故に発展しないように優先権を譲る」という考え方があります。
*梶は若かりし頃に トローリング(カジキ釣り)やシーバッシング(スズキのルアー釣り)の船長をしていました。
陸上では、海上ほど「機動力」の差はありませんが、バイクはクルマよりも俊敏で、短く止まれるのは確か*(訂正後→)バイクのほうが自由度が高いのは確か。
*註:「制動距離そのものはクルマのほうが圧倒的に短い」という指摘をいただいたので、上記を訂正しておきます。参考記事「バイクと車では急ブレーキ時の制動距離、停止距離はどちらの方が短いのですか?」
ならば、海運界にならって「陸上で最高の機動力を誇る乗り物を運転している者」として……歩行者や自転車、クルマを守ってあげる(保護してあげる)……気持ちをもってほしいという意味で「こちらが事故を避けてあげる」と表現しました。
そうすれば、敵対することもなく、みんなが仲良くやっていけるのではないでしょうか。
さらに言うなら……ドライバーさんに「渋滞での走行、ご苦労さまです」といった ねぎらいの言葉 をかけながら走っていれば、多少、幅寄せされることがあっても、おおらかな気持ちでいられます (^^)
昔から言われているように「注意1秒、怪我一生」……「急がば回れ」で、気持ちよく帰宅したいものですね。



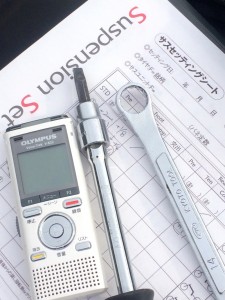






コメント