エンジンは煮物と一緒?! 温めて、冷まして、また温めて
「バイクを乗り換えたので、慣らしを兼ねたツーリングに同行してくれませんか?
サスセッティングや乗り方もアドバイスしてほしいんですけど……」
そんな依頼をいただいたので、
ツーリングパートナーとして、
東京から日帰りで志賀草津高原ルートを巡ってきました。
それにしても、志賀草津高原ルートから望む北アルプスは美しいですね。
いい景色、いい道、いい気持ちで慣らしをすれば、
それだけいいエンジンに仕上がるというものです。
—–ちょっぴり宣伝 「慣らし代行サービス」——————–
大型バイク専門誌の編集長を引退して、バイクショップに身を置いていたときに、
「慣らし代行サービス」を行っていました。
「サーキット走行会に行きたいんだけど、慣らしをする暇がない」
「プロの手で、いいエンジンを作ってほしい」
という方々から依頼を受けて、おおむね3日程度で
エンジンやタイヤ、ブレーキ、サスペンションを仕上げていたんです。
お返しするときには、ライディングポジションやサスセッティングを
オーナーさんに合わせ、そのバイクの特徴や乗り方のポイントを
まとめたレポートも差し上げていました。
今でも個別に請け負うことは可能なので、興味のある方は
info@k2biketravel.com までお問い合わせください。
———————————————————————-
せっかくですから、いいエンジンを作る慣らしのコツをお伝えしておきましょう。
【基本的な考え方】
エンジンにはアルミや鉄、ステンレス、チタン、銅、
樹脂、ラバーといった素材が使われています。
温度が上がったときの膨張の仕方はそれぞれ違いますし、
冷えていくときの収縮の仕方も、また異なります。
慣らしの過程では、これらが馴染み合っていくことが大切なんです。
だから
「温めたり、冷ましたりすることが重要」
と、世界的に有名なチューナーさんは教えてくれました。
ちなみに、その方がエンジンオーバーホールを請け負ったときには、
エンジンベンチで10時間ほど慣らしをしてから納品するそうです。
その運転パターンによって
パワーやレスポンスが変わると言いますから、奥が深いですね。
その後、様々な方に慣らしの方法をうかがい、
自分でも試行錯誤した結果、たどりついたのが、現在の方法です。
ミドルクラスのようにパワーが限られる場合は特に
梶(大型バイク専門誌 元編集長・K2 Bike TRAVEL ツーリング ナビゲーター)が
慣らしをするとトップスピードが伸びますから……
メーカーが指定する方法を尊重しながら、
「梶式」のエッセンスを取り入れてみてはいかがでしょうか?
【梶の慣らしのやり方】
Step1:0~100km
ハンドルやレバー、フットペダル、バックミラーの位置を
自分の体格に合わせたら、静かに走り出します。
100kmほどていねいに走ったら、
休憩してエンジンを人肌の温度まで冷やします。
ていねいと言っても、低回転でダラダラ走るわけではなく、
ガソリンをきれいに燃やすことに専念!
最高出力発生回転数の「3分の1」を上限にして、
気持ちよくエンジンが回る領域をキープすればいいでしょう。
まずはエンジンに、「回ること」に慣れてもらうイメージです。
燃料満タンでスタートし、
休憩中は異臭や液漏れがないかどうかを細部まで確認します。
Step2:100~300km
最高出力発生回転数の「2分の1」を上限にして、
各ギヤを、できるだけまんべんなく使っていきます。
梶は、自分のペースで走りやすい
夜の高速道路を利用することが多いので、
すべてのSA/PAをドライブスルーします。
SA/PAに入るときは、後続車に注意しながら
「6→5→4→3→2→1 」とていねいに1速ずつシフトダウンしていき
……止まらずにそのまま……「1→2→3→4→5→6」と
ていねいに加速して本線に戻るわけです。
スロットルは絞り気味(無暗にガバガバ開けない)にして
比較的一定のペースを保ち、ガソリンをきれいに燃やすことに専念!
ただ単にタイヤが転がっているという状況は極力作らず、
軽く負荷を掛けながら走っています。
具体的には、1kmぐらいかけてジュイ~~~~~~ンと
ジワジワ加速していくイメージ、あるいは
わずかに上り勾配の付いた道をじっくり踏みしめながら前進するイメージ、
走行風圧とバランスしながら(風圧をわずかに押し戻すように)走るイメージです。
スロットルを閉じるときにも、ジュイ~~~ンとていねいに戻します。
オドメーターが300km前後になったら給油して休憩。
燃費計が付いているなら、その数値と
「走行距離÷給油量=満タン法による燃費」のデータを照らし合わせて、
誤差を確認しておきます。
1回目の休憩と同様に、異臭や液漏れがないかどうかを確認しつつ、
エンジンを人肌の温度まで冷やします。
初日は、このあたりで終えてもいいでしょう。
Step3:300~500km
最高出力発生回転数の「2分の1」を上限に
ガソリンをきれいに燃やして走るところは同じですが、
徐々に負荷を大きくしていきます。
加速する回数を増やす、そして
加速するときのエンジン回転数の幅を大きくしていくイメージです。
その頻度は1km~数kmに1回といった感じでしょうか?
あまり神経質にならず、加速しながらエンジンを育てていくと
考えればいいと思います。
やがて、エンジンが軽く回るようになってきます。
オドメーターが500kmくらいになったら給油して休憩。
燃費データを再チェックします。
あるいは、燃料残量警告灯が点灯するまで走り続け、
何リットル入るのかを確認しておきます。
急いで慣らしを終わらせたい場合も、ここで一晩おき、
完全にエンジンを冷やします。
Step4:500~1000km
タイヤ銘柄によっては、
実走行でもまれて形が変化するのか、
空気圧がやや低下することがあります。
走行前にタイヤ空気圧を確認して
もし下がっているようなら、メーカー指定値に補正。
こうしたタイヤは、おおむね300kmほど走ると、
ハンドリングも空気圧も安定してくるので、心配はいりません。
あわせて、エンジンオイルの量と色(特に白濁が危険)、
冷却水の量、ブレーキディスクの色や
チェーンの張り具合も確認します。
エンジンや車体にオイルの飛散跡がある場合、
冷却水経路からクーラントがにじんで甘い香りがする場合、
ボルトが緩んでビビリ音が発生する場合、
ブレーキディスクが青紫色に焼けている場合は、
きちんと原因を究明して、対策します。
不安なら、購入したディーラーを訪ねてください。
問題がなければ、ていねいに走り出して、
エンジンとタイヤが温まったら、慣らし再開です。
Step3と同様に、負荷をかけながら
息の長い加速を心がけますが、ここでは走行100kmごとに
エンジン回転数の上限を1000rpmずつ高めていきます。
相応に速度も上がってくるので、
以前よりも1~2速下のギアを使うのが一般的。
大型バイクの場合は、かなりの速度になるので、
高速道路ではなく、中速コーナーを中心とした空いた
ワインディングロードをマイペースで走りながら、
1~3速でていねいに加速していくのも、ひとつの手です。
冒頭で、志賀草津高原ルートを選んだのも、
このあたりを考慮してのことでした。
タイヤやサスペンションにかかる荷重は大きくなり、
ブレーキの仕事も増えていきますから、
足まわりの慣らしも意識して進めます。
といっても、特別に何かをするわけではなく、
滑らかに大きな荷重をかけ、滑らかに荷重を抜くように心がけます。
一部の輸入車のように、極端な設定になっている場合は、
サスセッティングで補正することもあります。
やがて「慣らしはもういいかな?」と感じ始めるので、
そうなったら、以下の3点を意識的に探して、
潜在能力を引き出します。
■気持ちのいいスロットルの開け方と閉じ方
■バイクの動きに違和感のない着座位置
■不自然な抵抗を感じない倒し込みの方向
久しぶりにバイクに乗るときにも、
乗り始めにこの3点をチェックすると、いち早く勘が戻ります。
ディーラーが指定する走行距離(800kmまたは1000km)になったら
初回点検を受けて慣らしは完了です。
【追伸】 FI車は下手な友人に貸しちゃダメ?!
最近、当たり前になったFI(燃料噴射)のエンジンは、
自己学習機能の働きで、あなたのスロットルワークに
最適化されるようになっています。
裏を返せば、スロットルの操作が下手だと(粗いとか、一貫性がないとか)
出力特性も粗雑になりやすいということ。
これを教えてくれたのは、バイクショップにいたときのチーフメカニックでした。
梶…最近、試乗車のエンジンがガサついてきたんだけど、なんとかならないかな?
メカ…自己学習機能をリセットすればいいんじゃないですか、いろんな人が乗りますからね。
梶…本当だ、直った! コレだよ、コレ。このフィーリングがほしかったんだよ。
梶が慣らしをすると「いいエンジン」になるのは、
自己学習機能を考慮して きれいに燃やす スロットルワークを
心がけていることも大きいと思います。
ちなみに、リセット機能がないFI車を、元のいい状態に戻そうと思ったら
…(梶の経験では)…
適切なスロットルワークで500kmほど走らなければなりません。
中古で購入したFI車も、同様に、
500kmくらいかけてアナタ色に染め直していくといいでしょう。
つまり、キャブレターよりもあなたらしさが出やすい時代に
なったということです。
だからこそ、今回の記事を参考に、
気持ちのいいエンジンを育てていただければ幸いです。




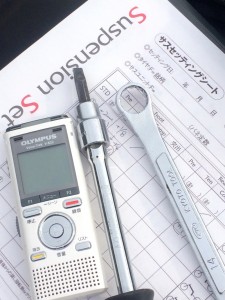






コメント
コメント一覧 (29件)
初めまして。
大変参考にさせて頂いております。
読み進めていて1つ疑問に思ったことがあるのですが、1000kmに到達するまでの間にオイル交換はしないのでしょうか?
これまでの取材を振り返ると、いろんな考え方が見つかります。
例えば、慣らしを始める前に「信頼できるオイルに換えろ」という方がいらっしゃいます。コンテナに入って海を渡ってくる輸入車のメカニックに、こうした意見が多いですね。
レーシングライダーの中には、1回ツーリングに行くたびに(300~500kmごとに)オイル交換する人もいます。レースでは練習走行が終わったらオイルを交換しますし、予選が終わった後も交換するので、その感覚からすれば「当たり前」。経済的に許すなら、この方法が理想的でしょう。
【1000kmでいいのでは?】
でも、大半の方は、メーカーが推奨する1000kmでオイルを交換すればいいのではないでしょうか? 特に、国内で生産された400ccクラス以上の国産車で、生産されてから数か月以内なら、1000kmで問題ないと思います。
逆に、生産されてから1シーズン以上経過した車両を、新車で安く購入した場合は、オイル交換してから慣らしに取り掛かったほうがいいかもしれません。保管状況にもよるので、購入したお店のメカニックに相談してみてください。
ちなみに、エンジンオイルの大敵は「ガソリンと水の混入」です。油温が十分に上がらない短時間走行ばかりだと、ガソリンや水が蒸発せず、オイル粘度が低下して、エンジン保護能力が下がってしまいます。
エンジンをいたわりながら(スロットルを無駄にパコパコ開けずに)ある程度まとまった距離を走る「慣らし」の場合は、油温が十分に上がってガソリンも水も蒸発するので、エンジンオイルの劣化は最小限に抑えられるはず。金属粉が混じらなければ、1000kmは十分に許容範囲だと感じます。
慣らしを請け負ったついでに、初回点検を代理受診することも多いのですが、最近のエンジンは工作精度が高いようで、金属粉が混じっているケースはまず見かけません。この点でも1000kmで良いのではないかと思います。
【大事をとるなら3回交換?!】
もし1万rpm以上回るエンジンで、熱的に厳しい(すごく熱くなる)なら、800km→1500km→3000kmと3回オイルを交換し、その後は3000kmごとにオイル交換していけばいいのでは? 僕が信頼するメカニックは、経済状況が許す限り、この3回交換(800km・1500km・3000km)をすすめています。
環境問題もあって、メーカー推奨エンジンオイル交換サイクルは「1万km」というバイクが多いですが、早めに交換するに越したことはありません。優れたメカニックは、オイル交換のついでに、いろんなところに目を配ってくれるので、3000kmごとにショップに持ち込むといいでしょう。
このスパンなら、燃焼して減ったオイルを継ぎ足す必要もないはずです(空冷エンジンと過走行車はエンジンオイルが減りやすいものです)。
【オイル交換で厳守してほしいこと】
もしシフトアップ/ダウンのフィーリングがザラついてきたら(渋くなってきたら)迷わずオイルを交換してください。ミッションギアの歯と歯が当たる部分の油膜が切れて、ギア表面がミカン肌のように荒れてしまう恐れがあるからです。
こうなると、いくらオイル交換しても、滑らかなシフトタッチは二度と戻ってきません。その前にオイルを交換して、ミッションを守ってあげてください。構造上、ミッションは油膜が張りにくいので、ガソリンや水の混入でオイル粘度が下がるとモロに影響を受けてしまうわけです。
もうひとつ気を付けてほしいのは、メーカー推奨のオイル粘度を守ること。オイルポンプやオイルラインの設計は「推奨オイル粘度」が前提になっているので、むやみに変えてはいけません。ただし、過走行車はシリンダーとピストンリングの隙間が広がっているはずですから、粘度が1ランク高いオイルを試してみる価値があります。
アイドリング回転数を下げるのも厳禁です。無暗に下げるとアイドリング時の油圧が低下し、クランクベアリングが摩耗してしまう恐れがあるからです。
頻繁に交換するからといって、安価なオイルを使うのも避けたほうがいいですね。100%化学合成油ならではの優れた清浄能力は、半合成油をどんなに頻繁に交換しても得られないものです。ただし、100%化学合成油はエンジンとの相性の良し悪しが出てくるので、ベストマッチのオイルを見つけ出す必要があります。
以前の愛車で気に入っていたオイルを、新しく買い替えたバイクに入れたら「いまいち」……ということも起こりうるのが、オイルの世界。高価なオイルほど油膜の設計が特徴的なので、メカニックに相談して、評判のいいオイルから試してみるといいでしょう。
【まとめ】
・一般的には初回1000kmでオイル交換を。
・大事をとるなら800km→1500km→3000km(以降3000kmごと)のスパンで。
・短時間運転、長すぎる暖機運転、無駄なスロットルオープンは避ける。
・シフトタッチが悪化してきたら、できるだけ早くエンジンオイルを交換する。
・メーカー推奨オイル粘度を守る(過走行車は1ランク硬いオイルも試してみる)。
・アイドリング回転数を無暗に下げない。
・愛車とベストマッチのオイルを探し出す。
エンジンオイルは「エンジンの血液」ですから、上手に付き合って、充実したバイクライフを送ってください。
丁寧な回答誠にありがとうございます。
夏頃にハスクバーナの新型VITPILENを購入予定なのでこの内容を参考に実施したいと思います。
はじめまして。
明日、納車を控え「慣らし運転」について調べていたところ、このWEBページを見つけました。
非常にわかり易い内容・表現で参考にさせていただいています。
ただ、1点質問があるのですが、「ガソリンをきれいに燃やす」という表現があるのですが、
これは具体的にどういうことなのでしょうか。
初めてのバイクで初めての新車ということで、せっかくであれば自分色の良いバイクに仕上げていきたいと
思います。アドバイスよろしくおねがいします。
昔からプロライダーの間でよく使われているのが「ガソリンをきれいに燃やす」という表現です。2スト250ccレプリカや2ストモトクロッサーに乗ると、燃焼の良し悪しを明確に体験できるんですが、今はそういうバイクが見当たりませんからね……f(^^;;
エンジン回転数の上昇が「もたつき」もせず、トルク感が「薄っぺら」にもならないようにスロットルを開けていく感じです。
消しゴムで字を消すときの「紙とゴムの接触感」がこれに近いかもしれません。力を入れてグイグイやると紙が傷みますし、力が弱すぎると紙の表面をゴムが滑って食いつきませんよね。程よい力加減と消しゴムを動かすスピードが揃った時に、気持ちよく字が消えます。
同様に、スロットルを開ける「大きさ(開度)」と「スピード」を意識して、そのときにベストな組み合わせを探してみてください。前述したように、もたついたり(スロットルを開ける量や速度が過大)せず、ピリピリしたり(スロットルを開ける量や速度が過少)せず、気持ちよくエンジン回転数が上昇していくような右手の動かし方を見つけていくんです。トライしているうちに、わかってくると思いますけど?
スロットルを開けるときも戻すときも、エンジンのご機嫌をうかがいながら! これが仲良くなるコツですね。
ありがとうございます。
経験が物を言うという感じですね。昨日納車され現在慣らし運転中です。
自分でも探り探り見つけていきたいと思います。
人生初バイクなので気がついたら慣らし期間が終わってるなんてことがないように
しっかり見極めていきたいと思います。
納車、おめでとうございます。
愛車を大切にして、末永くお幸せに~♡
はじめまして! バイクの慣らし運転について調べてたらこのサイトにたどり着きました。
CB400SF の2015年モデルの中古を納車予定の者です。
そのCB400SFの走行距離が500kmなのですが、その場合も Step4:500~1000km の走り方でいいのでしょうか?
どんな走り方をされているのかわからないので「Step 2」を50kmくらい実施し、ミッションタッチを確認してみてください。滑らかにシフトチェンジできるようなら「Step 3」を100~150kmしてから「Step 4」へ!
2015年モデルとのことですから、エンジンオイルが無交換のままなら、新品のエンジンオイルに交換してから慣らし運転をスタートしたほうがいいでしょう。
タイヤのサイドウォールに記載された「製造年&週」も要チェックです→https://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc/special/knowledge/post-9.html
2015年当時に生産されたタイヤだと、見た目は新品同様でも「グリップやダンピングは3割ダウン」程度のフィーリングになっていると思います。
ABS仕様ならまだしも、ABS未装着だと自転車等が飛び出してきたときに、驚くほど早期にタイヤがロックして「転倒」などにつながりますから……思い切って前後タイヤを新品に交換しておくことをオススメします。
梶はレンタルバイクを借りたときに、5年前に製造された「硬化した新品同様のタイヤ」が付いていて、痛い目に遭ったことがあります (^^;;
転倒修理コストや事故になったときの補償を考えると、タイヤを新品に交換したほうが、はるかに安上がりですね。
しっかり慣らしをしながら、フューエルインジェクションの自己学習機能にあなたらしいスロットルワークを覚えてもらって……いいエンジンに仕上げてくださいね。
返信ありがとうございます!
8月上旬納車予定なのでその時にオイルとタイヤについて聞いてみます!
慣らし運転は参考にさせていただきます。ありがとうございました!
初めまして。
現在、kawasakiネイキッド大型バイクを購入して慣ら中でございます。
こちらのページの説明が解り易かったので、それに沿って実施しているつもり
なのですが、新車での慣らしは初めてなので・・・。
レッドゾーンは10,000rpm~で、
現在は670km、回転は7,000rpmを上限にに時々そこまでじっくり回す。
を、行っております。(主に10~3速を使用)
説明では「500kmからは走行100kmごとに上限を1,000rpm上げて」と
なっておりますが、最終的には10,000rpm(レッドゾーン手前)まで行うのが
良いのでしょうか?
それとも8,000rpmくらいで終了した方が?とも思いまして。
バイク取説では
(0-350km/4,000rpm)
(350-600km/6,000rpm)
(600-1,000km/控えめな運転)となっているためご意見いただきたくおねがいします。
「とし」さん、新車購入おめでとうございます。
レースに出るなら 10,000rpmまで キッチリと慣らしをしたほうがいいと思いますが、その領域になると車速(走行スピード)がかなり高くなるので、それなりの場所と経験が必要になります。
そう考えると、8,000rpmあたりで慣らしを終えるのが、よろしいのではないでしょうか? ていねい&きれいに燃やす「スロットルワーク」で、「とし」さん色のエンジンに仕上げていくほうが、はるかに重要だと思いますよ。
さっそくのご連絡、大変うれしく感謝いたします。
せっかくの新車なので慣らしも楽しみながら良いエンジンに仕上がれば
と思っておりました。
当方、レースに出るようなこと考えておりませんので、
おっしゃる通り、自分にとって乗りやすい仕上がりが目標です。
これで目標が決まり、残りの慣らしを楽しみたいと思います。
※蛇足ですが、慣らしで段々と上限回転数を上げていってるので私の感覚では
燃費がガンガンと落ちるだろうと思っていたのですが
プラスマイナス1km/Lの範囲くらいであまり変わっていません。
これは何と言いうか当りが出てきた効果と上限回転数upがバランスされたような
結果のでしょうか?
「とし」さんの、燃費に関する質問にお答えします。
現代のフューエルインジェクション(燃料噴射)車の「燃費」を大きく左右するのは「スロットルワーク」です。
エンジン回転数や車速(走行スピード)が高くても、「スロットル開度」が少なく、しかも一定のスロットル開度を「維持」していれば、瞬く間に「空燃比」が薄くなる(燃費が良くなる)ように、現代のバイクはプログラミングされているんです。
逆に言えば、パコパコとラフにスロットルを開ける(加速すると)と、燃料(ガソリン)がくべられて(噴射されて)、燃費が悪くなります。エンジン回転数そのものよりも、無駄なスロットルワークのほうが、燃費を悪化させるわけです。
ちなみにリッタークラスの並列4気筒車なら、通常走行の大部分は「スロットル開度 10%以内」に収まるでしょう。この範囲内を緻密に滑らかにコントロールしていれば、燃費は悪化しませんし、エンジン内部もきれいに保たれます。
ただし、高めのギヤ(5~6速)で、ずっと低回転(おおむね3000rpm以下)を維持していると、燃焼室やサイレンサーにカーボン(煤=すす/燃えかす)が溜まりがちになりますから……高速道路や峠道では中高回転域まで滑らかに加速したり、中高回転域を維持したりして(高回転巡航時のスロットル開度は大きくなくてもOK)、エンジン内部をきれいに保ってください。
こうして走行距離を重ねていくと「ガソリンがきれいに燃えている」というのが、どんな状態なのかが、感覚的にわかってくると思います。
燃料消費について解りやすい説明、ありがとうございます。
納得です。
慣らしを終えた後も、この説明を参考に良いエンジンを維持するように
楽しんで行きたいと思います。
お役に立てて、よかったです。
充実したバイクライフを!!
「とし」さんにお目にかかれる日を、楽しみにしています。
新車購入まして、慣らしに差し当たって、こちらの記事を参考にさせていただきました。
色々な記事を読み漁りましたが、こちらが一番わかりやすく、また的確に書かれていると感じています。
慣らしも無事に終わり、車両は快調そのもの。乗るのが楽しいです。
ありがとうございました。御礼申し上げます。
新車購入、おめでとうございます。
この記事が役に立って、よかったです。
縁があって出会った相棒さんと
末永くしあわせに過ごしてくださいませ♪
陰ながら応援しております。
今後、走行距離が進んで
「人車一体感」が薄くなってきたときには
タイヤの空気圧と摩耗状態、
ステムベアリングの作動状態をチェックしてください。
このあたりは、近いうちに記事にしたいと思っています。
GSX-S1000を購入し、現在慣らし中です。参考にさせて頂いてます。
かれこれ10年以上バイクに乗っていますが、慣らし終盤にカーボン除去効果があるガソリン添加剤は慣らしに対して有効でしょうか?
信頼している「オイル開発者」によれば、著名オイルメーカーが発売している添加剤以外は「百害あって一利なし」とのことです。
たとえばエンジンオイル添加剤の効果を実感するとしたら、添加剤の溶媒で「元々のエンジンオイル」の粘度が低下したことが主因であって、エンジンの摩耗が促進されてしまう恐れもあるといいます。
一方、著名オイルメーカーが販売している添加剤は、コストの問題で「入れたくても入れられなかった」成分を別売りしているものなので「安心して使ってほしい」とその開発者は話していました。
バイクメーカーのエンジン開発者も「添加剤不要」と口を揃えますね。
実際に、ガソリンをキレイに燃やすような運転(適切なギヤで走り、スロットルをガバガバ開けない&無暗に低回転域の走行を続けない)を心がけていれば、カーボンが蓄積することもないと思います。
ちなみにFI(フューエルインジェクション)仕様の場合は、走行1万km程度でインジェクター(燃料噴射装置)の摩耗が問題になってくるので、レースのトップチームはインジェクターそのものを定期交換すると聞いています。ただ、公道でのツーリングが主体なら、そこまで神経質にならなくてもいいでしょう。
本題のガソリン添加剤ですが……僕がバイク月刊誌の編集長を引退してバイクショップに勤めていた時代に出会って以来、愛用し続けているのが『ニューテック・NC-220』(https://amzn.to/3b6F9aG)です。
リッタークラスだとわかりにくいかもしれませんが、250ccクラスに入れると「明確なトルクアップ」と「クリーンな燃焼」を実感できますね。僕は走行5,000kmを目安に使い続けていて……トラブルフリー&エンジン快調です。
僕は使用経験がありませんが、よく知るメカニックは『ワコーズ・フューエルワン』(https://amzn.to/356n4po)も効果的だとのこと。
というわけで、走行5,000kmを過ぎたあたりで、どちらかを試してみるといいのではないでしょうか?
丁寧な解説ありがとうございます。
5000kmで試してみたいと思います。
過去オイル添加剤は試した事がありませんでしたので検討してみたいと思います。
何より適切な慣らしが大切という事ですね(^^)
返信ありがとうございました(^^)
はじめまして!
バイクを初めて新車購入するので慣らし運転について調べていました!とても参考になりました✨
ただ、私のテクニックで同じようにできるかは謎ですが見よう見まねでやれることはやってみようと思います!FI車ってあんまりおもしろくないと思ってたんですけど、こういう楽しみ方もあるんですね♪
ありがとうございました!いきなり失礼しましたm(_ _)m
お伺いするのを忘れていたのですが、カブのようなクラッチがないバイクでの慣らし運転も同様でしょうか?
はい、同じです。
バイクは「バランスの乗り物」なので……
125ccクラスであっても
「スロットル パカパカ」(X)
ではなく
「始めジンワリ 後からシッカリ」(○)
という、
ていねいなスロットルワークを心がけてくだされば
安心して気持ちよく走れますし
疲れにくいですし
エンジンやタイヤも長持ちします。
首都圏にお住まいでしたら、ご一緒にツーリングでも♪
はじめまして
先日、1万㎞の走行を機に愛車(2スト80cc)の腰上 &クラッチ周りのOHをしました。今後の慣らし運転について知見を求めて検索しこちらへたどり着いた次第です。
慣らしについての基本は排気量を問わず同様と考えますが、速度域が異なる小排気量の場合はどのようにしたら良いでしょうか?
エンジンを開けたときの
ピストンヘッドや燃焼室の状態はいかがでしたか?
チャンバー(排気管)やキャブセッティング
との兼ね合いもあるので
一概には言えませんが
黒いカーボンがこびりついているようなら
スロットルワークを見直してみるといいでしょう。
特に2ストは、ラフなスロットルワークをすると
余分な生ガスが送り込まれてしまい
「吹け」が鈍くなる=加速が鈍くなる
うえに、カーボンが堆積してしまいますからね。
昔は「絞り気味」なスロットルワークが
必須とされていたものです。
パカパカ開けて「生ガス」を食わせちゃいけない!
それが先輩たちの口癖でした。
言い換えると、
エンジンの回転上昇を追い越さないように
スロットルをていねいに開け、
かといって開け足りなくもならないように(特に中~高速域)
エンジンと対話しながら右手を操る。
ここが2ストの面白さだと思います。
僕が尊敬するメカニックたちは
オーバーホール時に以下の点(2スト/4スト・排気量問わず)に
こだわっている方が多いですね。
●できるだけ抵抗なく上下運動できるピストン位置
(ヘッドを載せる前にシリンダーの最適位置を探す)
●シリンダーとヘッド接合部の平面性
(スタッドボルトに掛けるナットのトルク管理が独特)
(プリセット型トルクレンチを嫌うメカも多数)
●クラッチの重量バランス
(普通に組むと偏心してエンジンの吹け上りが鈍くなりがち)
●スパークプラグ接地電極の位置
(ヘッド固定時の接地電極の向きと燃焼室内のタンブル流との関係)
特に小排気量車は、こうした効果が顕著に表れるものです。
ドライブテェーンやホイールベアリング、
ブレーキキャリパーの整備状態も重要で……
かつてのGP125では、担当メカニックの技量によって
加速や最高速度が伸びたり伸びなかったりしたものです。
こんなわけで、
オーバーホール時に全てのパーツが
あるべき位置にきちんと収まっていれば、
ていねいに初期馴染みを取る程度で
すみやかにパワーを発揮し、
気持ちのいいエンジンになっていくと思います。
その方法はブログで示した通りで、排気量による差はありません。
ただし、小排気量だと慣らし中に出せる速度が低くなるので
幹線道路での慣らし運転は難しいかもしれませんね。
割り切って、夜中など、通行量の少ないときに
慣らしを行ってしまうといいでしょう。
ちなみに某メーカーの開発者は
「ウチのエンジンは組み立て精度が高いので、
慣らしは100kmもやれば十分」
と言っていました。
特に腰上オーバーホールは
ミッションなどの慣らしは考えなくてもよいので
エンジンが滑らかに気持ちよく吹けるようになったら
ひと区切りと考えていいと思います。
逆に、何か違和感を覚えるようなら
それは慣らしの問題ではなく
「組み方」の問題が大きいと思います。
こんなときには、先人たちの知恵を学んだり
構造を理解してより良い組み方を試してみたりすると
バイクライフの幅が広がって面白いでしょう。
ただ、2ストの神業的メカニックは
めっきり少なくなってしまったのが残念ですね。
YUZOチャンバーの柳沢雄造さんも故人ですし……。
生前には柳沢さんのファクトリーで興味深い話を
たくさんうかがったものです。
現代なら、OXレーシングの田島さんが頼れる存在です。
http://ox-racing.net/(東京都江戸川区)
アッ、仕事を依頼するときには
値切らずに、きちんと報酬を払ってくださいね。
ゴッドハンドが幸せに暮らしていける環境を整えることが
僕たちだけでなく、後世ののバイクライフを
豊かにすることにつながりますからね。
はじめまして。
記事を読ませていただきました。とても参考になります。
一つ質問があるのですが、慣らし期間中(走行距離1000kmまで)にオイル交換をした方が良いと聞いたことがあり、350km、600km、1000kmでオイル交換をしようと考えているのですが、これはエンジンにとっては良いことなのでしょうか?
kawasakiのNinja H2を新車で購入する予定で、できる限り長く乗っていたいので、どうかお答え願います。
Ninja H2の購入、おめでとうございます。
「エンジンの慣らし運転」に関する学術論文は見たことがないので(お金をかけて研究する意味が薄いからでしょう)、エビデンスを問われると困りますが f(^^;; ……
専門家=オイルメーカー&開発者・バイクメーカー&開発者・エンジンチューナー・レーシングチーム&メカニック&ライダーに取材してきた経験から総合的に判断すると、以下のようになります。
●オイル交換は頻繁に行うほどいいのですが、コンマ1秒を争うレースならともかく、ツーリングが前提であれば、そこまで手間とコストをかけてエンジンオイルを交換する意味=費用対効果は薄い。むしろ「走り方」「エンジンオイルの選び方」(いずれも後述)に注意したほうがいい。
*参考:レースなら、毎セッションあるいは毎日、エンジンオイルを交換するのが一般的です。
*参考:元GPライダーはツーリング(150~300km程度)に行くたびに愛車のエンジンオイルを交換していますが、それはエンジンオイルのサポートを受けているからであって、一般ライダーには「お金がかかり過ぎるから、そこまでしなくてもいい」と話しています。
●慣らし期間中に頻繁にエンジンオイルを交換すると、初期馴染みの際に生まれる超微粒子による「馴染み効果」が薄くなってしまい、「かえってよくない」と考えるエンジンチューナーやレーシングメカニックもいます。刃物を研ぐときに「砥石と包丁から生まれる超微粒子」を洗い流してしまうと、刃物を研げないのと同様の理屈と考えればいいでしょう。感覚的には理解できますが、本件についてのエビデンス(研究報告や学術論文)は見たことがないので、正確なところはわかりません。
●慣らしに大きな影響を与えるのは、部品設計(通常運転温度域で各パーツのクリアランスが期待通りに維持される形状や材質かどうか)と工作精度(組み立て時のクリアランス管理)です。この点では、CAE解析が進み、表面処理技術も高く、工作精度に優れた(パーツ単体の生産もエンジンの組み立ても)現代の中大型バイクは「慣らしに神経質にならなくてもいい」と話す開発者が大半です。「ウチのバイクは100kmで十分」と話す開発者さえいます。
●輸入車を中心に扱うメカニックの中には、最初に入っているエンジンオイルを「すぐに交換しないほうがいい」と話す人もいます。バイクメーカーが工場出荷時に充填するオイルは「慣らしに有効な性質&成分を持っているから」というのがその理由ですが、メーカーに確かめたことがないので、真偽はわかりません。
●結局のところ、現代の中大型バイクであれば、それほど神経質にならずに「オーナーズマニュアルが指定するエンジンオイルと交換サイクル」に沿うのが、品質保証(故障時のクレーム対応)の面でも安心だと思います。
ただし、以下の場合はエンジンオイルの性能低下が進みやすいので、あえて交換サイクルを短くしたいですね。
・油音が上がりやすいバイク
・空冷エンジンのバイク=ピストンとシリンダーのクリアランスが広い&シリンダーヘッドが高温になりやすい
・チョイ乗り(1回の走行距離がおおむね100km未満)が多い
・渋滞に巻き込まれることが多い
・市街地走行が多い
・安価なエンジンオイル(鉱物油や半合成油)を入れている
もし年間走行距離が少なければ、下記のように「年2回」のエンジンオイル交換がおすすめです。
・「春」に交換=冬季のクランクケース内の結露による水分混入&低温運転時のガソリン混入によるオイル劣化に対処
・「秋」に交換=夏季の高温運転によるオイル劣化に対処
年間を通じてそこそこの距離を走るのであれば下記の走行距離を目安にオイル交換するといいでしょう。
・走行「2500km~3000km」=空冷エンジンの場合 / 市街地走行やチョイ乗りが多い場合
・走行「5000km」=ツーリング主体の場合(もっとも一般的な目安)
・走行「10,000km」またはバイクメーカーが指定する交換サイクル=高速道路を利用したロングツーリング(1日350~500km)が主体の場合
オイル交換の際は、行きつけのバイク屋さんで「定期点検」も行ってもらうと万全です。特に以下の点を見てもらうと安心ですね。
・ブレーキパッドの残量や引きずりの状態
・チェーンの張り具合や給油状態
・ステムベアリングの作動状態
・ホイールベアリングの作動状態
・リヤホイールハブダンパーの状態
・リヤサスペンションリンクまわりの作動状態
・オイルや冷却水の漏れとにじみ
・重要保安部品のボルト&ナットの緩み
・各部のサビ
そうそう、タイヤの空気圧と摩耗具合は、走行前にご自身で毎回チェックしてくださいませ。
●走り方について……大型バイクで特に避けたいのは、すぐにシフトアップして極低回転(アイドリング+α)で走り続けることです。昔気質の口の悪いライダーは「それじゃ、永遠に慣らしじゃん」などと表現しますね(笑)。
空燃比を緻密に制御できる現代のFI車(燃料噴射装置を採用したバイク)であっても、10,000rpm以上回るエンジンを3000rpm以下でしか走らせていないと、どうしても燃焼室にカーボンが堆積しやすく、ゆくゆくはエンジン性能の低下を招いてしまいます。マフラーを交換している場合は、サイレンサーにカーボンがたまって吸音効果が低下しているケースも多いそうです。
「きれいな燃焼」と「クリーンな排出ガス」のためには、できるだけパワーバンド(レッドゾーンが10,000rpmから始まるエンジンなら6000~9000rpmあたり)で運転したいところですが、大型バイクの場合は速度が出過ぎて「赤キップ=免停」を免れないのが、悩みどころですね f(^^;;
記事に書いたように、郊外のクルマの流れに乗っているときには「絞り気味」のスロットルワークで「燃料を喰わせ過ぎない」ように注意し、低rpmであってもエンジンを「きれいに燃やす」ように配慮してくださいませ。
●エンジンオイル交換を怠った場合……最も悪影響を受けるのはミッションタッチでしょう。オイルの性質上、スライドする部分は油膜を張りやすいので「ピストン-シリンダー間のトラブル」はほとんど起こらないと思いますが、回転する部品がかみ合うミッションやバルブまわりでは油膜切れが起こりやすく(特にアイドリング回転数をメーカー指定値より下げた状態で長時間アイドリング運転をした場合)、金属表面に「ミカン肌」のような荒れが出てしまうことがあります。
こうなると、滑らかなミッションタッチは二度と戻らないので、走行距離にかかわらず「なんとなくミッションタッチがガサつき始めたなぁ」と感じたら、速攻でエンジンオイルを交換してください。
●エンジンオイルの銘柄について……エンジンの清浄力については「100%化学合成オイル」に勝るものはなく、鉱物油や半合成油をどんなにマメに交換しても、100%化学合成オイルほどの清浄力は得られないと聞いています。ただし、100%化学合成オイルは「味付け」が多様で、愛車のエンジンとの相性の良し悪しが出てきます。
たとえば「薄目でピンッとした油膜を張るオイル」はスロットルレスポンスに優れ、パワーも出やすいのですが、水分混入やガソリン混入には弱く、耐久性はそれほど高くありません。逆に「厚目で弾力性のある油膜を張るオイル」は水分混入・ガソリン混入・温度変化に強く、終始、まったりとした穏やかな運転フィーリングを示します。
こうした性質は、カタログやオイル缶などに書かれていますので、「うたい文句」を参考に使ってみて、好みの銘柄を探し当ててみてください。これも「楽しみ」のひとつです。
ちなみにオイル銘柄を変更する場合は「エンジン内部に残ったオイル」と「新しく入れたオイル」が化学反応を起こして、大幅に性能が低下してしまうケースが「まれ」ではありますが、起こり得ますので……オイルフィルターも同時に交換してくださいませ。
そうそう、バイクメーカーが指定するオイル粘度は必ず守ってくださいね。オイルポンプやオイルラインの設計は、その粘度を前提にしているので、「燃費をよくしよう」などと思って4輪車で流行している低粘度オイルを入れると、エンジンの耐久性を著しく損なう可能性があります。
もしバイクメーカーの指定粘度に幅がある場合は、以下のように考えるといいでしょう。
・高めの粘度を選びたいケース=総走行距離が多め、渋滞路走行が多め、市街地走行が多め、ねっとりとしたミッションタッチが好き
・低めの粘度を選びたいケース=鋭いスロットルレスポンスが好き、俊敏に加速するのが好き、冬季の始動性を高めたい
●まとめ……もし僕が「Ninja H2」を購入するなら
1:納車後に高速道路を利用して「500km程度」の慣らしツーリングに出かけ
2:翌日に、やはり高速道路を利用してエンジン回転数を段階的に高めながら「350km」程度の慣らしツーリングをして(総走行距離850km程度)
3:そのまま初回点検を受け、エンジンオイル&オイルフィルターを交換してもらいます。
4:翌週にツイスティロードを主体にした日帰りツーリングに出かけ、サスペンションやブレーキ、タイヤを馴染ませながら、それらの特徴(性質)をつかんで
5:エンジンモードをひと通り試し、各モードの特徴を確認して
6:サスペンションセッティング、タイヤ空気圧、エンジンモードを好みに合わせる
というプロセスを取ります。
次のオイル交換は「3000km」でしょう。その後は「5000km」ごとにオイル交換と定期点検を受けると思います。
タイヤ空気圧の調整、ドライブチェーンの給油、ブレーキパッドの残量確認、オイルや冷却水の確認、ボルト&ナット類のゆるみチェックは自分でマメにやりますね。
保管時は「燃料ほぼ満タン」を維持し(結露による水分混入を防ぐため)、ギヤを1速に入れてサイドスタンドで立てておきます(大きな地震がきてもバイクが倒れないようにするため)。
以上、参考になれば幸いに存じます。
追伸
Ninja H2は、ライダーの下半身が熱風にさらされるバイクなので、低温火傷しないようなライディングブーツ&ライディングパンツを着用してくださいませ。
市街地での低速走行や渋滞路走行では、その熱さが耐え難くなるケースも出てきますので、ツーリングの際には「市街地や渋滞を避ける」ルートや走行時間帯を選ぶといいでしょう。
もし「快走できない」状態が繰り返されるようなら、以下を考慮してください。
・耐久レース用途を意識した「高温に強い100%化学合成オイル」を選ぶ
・バイクメーカーが指定する範囲内で「高目のオイル粘度」を選ぶ
・比較的短いサイクル(3000km程度でしょうか)で交換する
老婆心ながら付け加えておくと、4輪車用オイルをバイクに入れてはだめですよ。
4輪車用エンジンオイルは、バイク特有の「ミッション&クラッチ」には適合しないので、必ずバイク用エンジンオイルを使ってくださいませ。